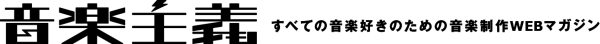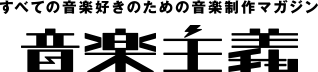野外フェス開催の裏側
力竹総明さん
“RUSH BALL”プロデューサー
大阪で8月に2デイズで開催された野外フェス“RUSH BALL 2020”。参加を関西圏在住者に限定し、1日の入場者数を5,000人までと縮小、感染症対策も徹底し、さらに場内にはソーシャルディスタンスを保つための柵も設置と、これまでにない形での開催となった同フェスの裏側について、プロデューサーに聞いた。
ライブハウスを残す理由と、次の結果につなげる方法、
それが次に考えるべきことなんじゃないかなと思っています。
正解はひとつじゃない。葛藤の中で、
止める理由を探すより、やる方法はないかと考え出した
8月29日と30日の2日間、大阪府泉大津市で野外フェス“RUSH BALL 2020”が開催された。全国各地でライブやコンサートの中止が相次ぐ中、初めて開催された夏の野外フェスとなる。
参加を関西圏在住者に限定し、1日の入場者数は5,000人までと例年の2万人から観客動員数を大幅に縮小。Web問診票の記入や大阪コロナ追跡システムの登録、入場時の検温など、ガイドラインに沿った感染症対策を徹底し、会場でも大声での声援や接触行為を禁止、ソーシャルディスタンスを確保するための柵を設置するなど、これまでにない形での開催となった。
コロナ禍での新たな形でのフェス開催に至った裏側について、そこで得た経験について、“RUSH BALL”プロデューサーの力竹総明さんに話を聞いた。

“RUSH BALL 2020”の開催から2週間が経った9月14日にはイベントによる感染やクラスターが発生しなかったことが発表されました。無事に開催された結果を受けて、まずどう感じてますでしょうか。
無事2週間を超えられて、長かったなあというのが率直な意見ですね。
フェスが終わった後も、なかなか安心できる日々ではなかった。
ステージを降りてくるアーティストを迎えてライブを無事終えたときにも、達成感はありながらも、まだ「2週間」というキーワードが残っていて。8月30日、イベントが終わった翌日からまた見えない何かと戦っていくみたいな2週間でしたね。
来場してくれたお客さんもきっとそうだったんじゃないかと思います。土日に開催させていただいたんですけれど、終演後の会食は極力控えてもらうアナウンスをしました。窮屈な客席だったであろうし、普通だったら繁華街に出て、その日の感想を共有すべく飲みに行ったりご飯を食べに行ったりすると思うんですけれど、それも控えてもらうようお願いをした。お客さんもそういったことを汲んでくれたんじゃないかなと思います。
日本だけでなく、コロナ禍に野外フェスを有観客で開催した例は世界的にも数少ないと思います。そういう中で“RUSH BALL”の開催はかなりの影響力を持つと思うんですが、そのあたりはどんなふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
コロナに関して、大学の先生や医療関係の先生とか、いろんな人がおっしゃる対策は、いろんな学説があったりいろんな方法論があったりしますよね。その全部が正解だと思うんですけど、その正解がすべて同じベクトルには向かっていないと思うんですよ。だから、止めるというのも正解だったと思うんです。
実際、この夏はフェスを中止や延期、もしくはオンライン開催に切り替える主催者がほとんどだったと思います。
いろんな人が関わっていると思うし、もちろんミュージシャンありきだと思うので。そう考えたら、さっき申し上げたように、正解はひとつじゃない。そういう葛藤の中で、止める理由を探すより、やる方法はないかなあっていうのを漠然と考え出したところから始まりましたね。
行政からの「ここまで徹底してやってもらえるんだったら支援します」の言葉が最後の決め手
紆余曲折あったと思いますが、開催に向かった最大の転機は?
大阪に関していうと、この厳しい状況になった中で、6月7日に大阪のBIGCATというライブハウスで、無観客で無料配信のライブを初めて行政と一緒にやったんです(“大阪府文化芸術活動(無観客ライブ配信)支援事業 PR LIVE -ACCESS CODE OSAKA!-”)。そこから始まって、7月、8月と、関西の8イベンターが集まって、イベントを行っていったんですね。状況によって、配信を入れながら、ハイブリッドでイベントをやってみたり、大阪城ホールでみんなで手分けして“Osaka Music DAYS!!! THE LIVE in 大阪城ホール”(8月8〜9日)というイベントをやってみたり。そういう状況を一個一個みんなでクリアしていく流れもありました。
そのノウハウを、これなら野外にも流用できるなとか、こういう業者さんは必要だなとか、どうやってそのギャップをクリアしようかを考えていった。そうして、最終的には地方自治体、つまり行政の判断ですね。市民を守る、府民を守る、住民を守るのが行政の最大の役目なので。
地方自治体というと、具体的には?
大阪府の港湾局の方と、泉大津市役所の方ですね。そこに新しく作ったガイドラインや、「こういうふうにやったらできるんじゃないだろうか」という方法論を何度か投げかけさせていただいて、行政の方に「ここまで徹底してやってもらえるんだったら、市民も含めて、協力的に話を進めて支援する」と言っていただけた。それが最後の後押しでした。
今まで行政や市民の方と友好的に15年ぐらいやらせていただいているので、今年無理してやって、来年以降にできなくなるのはつらいですし。でも、「こういう形でできないか」という打開策を提案して話をさせてもらったときに、「これからも協力させてもらいます」というメッセージをもらった。そのときに「これは開催しよう」と決めました。
それがいつ頃の段階でしたか?
7月の中旬ですね。8月1日には発表しないといろんなことが間に合わない状況もあったので。そこで出演者にも仮でオファーを出しているんですけれど、その時点でも「本当にやるの!?」って感じでした。なので、アーティスト側にも7月29日というデッドラインを決めて、その日までに行政からNGが出たり、緊急事態宣言、大阪モデルの赤信号が出たりしたら止めるつもりだ、と。そこまで腹をくくっていたんですけど、その時点で行政の後押しがもらえて、やる決断をしました。

ガイドラインは、WESSの若林さんが投げかけてくれた北海道でのガイドラインを参考に
アーティストやマネジメントの反応や意見はどうでしたか?
みんなバラバラでしたね。最後まで「やるの?」っていう人もいれば、「リッキー(力竹さん)が決めるならなんとかするんでしょ、出るよ」っていう人もいれば、「とりあえず先の状況を見ながら、状況に合わせて、行けそうなら行く」という人もいた。いろんなパターンがありました
ほぼ全員東京からの来阪なので「まず東京から移動していいの?」って言われて。「PCR検査を受けるの?」とかいろんなことを言われたんですけど、基本はこっちで考えるWEB問診とか、いろんな方法論を提案するから、それで体調管理して、状況を見て、それで移動してきてくれと。発熱があったり体調が悪かったらキャンセルしようと。それぐらいの覚悟をお互いに決めながら臨んだ感じです。
お客さんともアーティストとも、この状況で野外フェスをやることに対しての、高いレベルでの約束事を共有する必要があったということですね。
まず前例がないじゃないですか。何かを真似すればいいというものがゼロですから。もちろん、城ホールで5,000人のライブをやれたので、それはすごく大きかったです。屋内とはいえ、ひとつのルールができた。じゃあ、それを野外という環境でどう書き換えようか、と。やらないといけない必要最低限の部分と最大限の部分を盛り込んで、やれるんじゃないかって。
蓋を開けてみたら大変でしたけどね。たとえばWEB問診に関しても、6月の時点でGoogleフォームを利用して独自で作ったんです。お客さんも簡単に使えるし、WEB上で管理できて、個人情報も洩れない。それを“RUSH BALL”にも使おうということで、お客さんだけじゃなく、アーティストも、現地のクルーも、全員使いました。
何をやるべきか、ひとつひとつ決める作業から始まったということですね。ガイドラインはどのようにして決めていったんでしょうか?
ガイドラインに関しては、“RISING SUN ROCK FESTIVAL”をやっているWESSの若林(良三)さんが投げかけてくれた北海道でのガイドラインがすごくわかりやすかったので、参考にさせてもらいました。
それで作ってできあがったんですけれど、インナーで共有するだけじゃなくて、全員で見たほうがいいんじゃないかと思って。それでホームページで告知して、アーティストも、クルーも、お客さんも、参加者全員でガイドラインを確認していこう、と。そこにいろんなことを盛り込んで当日に向かった感じですね。情勢も変わっていったんで、どんどん更新していって。最終的には第四稿までリライトしました。( https://www.rushball.com/guideline/guideline.pdf )
当日、会場の設営やオペレーションも非常に大変なところだったと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。
やっぱり気温が高いので、警察、消防や関係各所と打ち合わせするときも熱中症の対策がメインになりました。もちろん感染対策はしているわけなんですが、熱中症になると体温が上がる。そうすると37.5度以上の熱が出る。たとえば仕込み中もスタッフが熱を出したんですけれど、だいたい熱中症はきちんとケアして1時間もすれば熱は下がるんです。今回は功を奏して、熱が下がらなかった人はいなかったんですけど、それも、気が気じゃない感じでした。
動員に関しては、国が定めた5,000人の規模で、背に腹は代えられないので、今までやっていたステージとは違う形で、とはいえちょっと見栄を張るギリギリのところでアイデア出しながらステージを組んで。熱中症のことを言われるので、毎年は日除けもないんですけれど、今回は日除けを作ったり、今年限定でエリアを設けて日傘もOKにしたんです。新しいことばっかりでしたね。
飲食やグッズ販売についてはどうでしょうか。
グッズ販売、飲食販売、クロークは、どれも飛沫防止のためのアクリル板や消毒液を置いたり、非接触電子マネーを導入したりしました。飲食は、いつも30店舗くらいあるところを、今年は5,000人に合わせて10店舗だけにしたりはしましたね。

細美武士が「マスクの向こう側で笑っているのを想像しながらライブするよ」とMC
ソーシャルディスタンスを保つため、1人ずつスタンディングで区切る柵も設置されていました。
あれも、僕が紙にペンで「こんな感じちゃう?」って書いたところから始まっていて。いろんなアイデアもあったんですけれど、ライブハウスに近い方法ってなんやろ?ってずっと考えていたんです。で、思いついたのが、大阪城ホールとかZeppでアリーナに並んでいる鉄の柵で。これをたくさん並べたらいけるんじゃないかって。
打ち合わせの翌日に現地に行ってバリケードを用意してもらったんですけれど、全部鉄柵じゃ無理だろうと。そうしたら業者が緑の網を用意してくれた。仕込みの2日目から4日かけてずっと客席を作ってました。
強度は大丈夫でしたか?
8割くらいのスタッフは、ライブで音がバーンって鳴って、アーティストが「来いよ!」って言ったら、みんなワーって行くんちゃう?って想像してました。でも、初日の2バンド目が終わったぐらいから、運営用のトランシーバーが鳴るようなこともなくなって。最初は「ここは密になるからこう移動してください」みたいに言うこともあったんですけれど、すぐにお客さんも空くのを待ってから入ってくれるようになった。本当に、お客さんに救われた!と思いました。
お客さんにとっても、この状況で野外フェスが開催されるのが異例であるというのを共有してくれているがゆえに、フェスを成立させるための意識を持ってきてくださった。
そうじゃないと成立しなかったと思いますね。特に2日目はアーティストが荒くれ者ばっかりだったので。運営チームに「力竹さん、ステージ袖に行っておいてください」って言われてたんです。アーティストが煽ったらお客さんが来るかもしれないから、アーティストが煽らないようにしてくれ、と。でも、ミュージシャンが口々に「今はこれでしかできないけど、まともじゃないこともわかってるし、今はこれでやってみて」とか、細美(武士)くん(MONOEYES)が「マスクの向こう側で笑っているのを想像しながらライブするよ」とか、言ってくれて。そういうメッセージがすごく刺さっているだろうなって、終始感じていましたね。


ここまでやれば、ライブハウスも大丈夫じゃんっていうオチが1ミリでもついてくれたら
本来は2万人で開催していたイベントを5,000人でということだと、収益としてはなかなか難しいものだとも思います。それよりは開催できたという実績を残すことを選んだということでしょうか。
ほかの公演もそうですけど、ライブハウスも、いろんなアリーナクラスのライブもなくなり、大阪ではなんとかみんなでやっていこうとしているところなんですね。そうやってライブの現場が弱ってきたときに「今、こういう形でやりました」というものがないと、来年にゼロベースで考えないといけないという思いがすごく強くて。だったら“RUSH BALL”で、やれる方法でやってみました、という。
しんどいけれど、でもこういう形でやれたということを残そうということですね。いわゆる「やったった!」にはならないようにしたいと。
来年に向けてのいい意味でのたたき台になった、というか。
そうですね。今、事後報告書とか、いろいろな書類を作っているんですけど、そこの冒頭では音楽業界やフェスをやっている人たちに、まず謝っているんです。こんな形でしか開催できなくてすみません、って。もっと自由度があったり、もっといっぱい方法論があったのに、時間のない中でこういう形でしか開催できなかったっていう自責の念はあります。
もっといい方法はあると思うし、お客さんにしてみれば「マスクしてるのに歌えない」とか「野外なのに、三密じゃないのに、制限されているのはなんで?」っていうところを打破したいなって。ここまでやれば、ライブハウスも大丈夫じゃんっていうオチが、1ミリでもついてくれたらなっていう思いでやり切った感じです。
実施報告書がホームページに掲載されていますが( https://www.rushball.com/guideline/rushballreport_0918.pdf)、印象的だったのは、英語、フランス語、台湾語と、各国の言葉で書かれていますね。これは、日本だけではなく、世界中でフェスティバルがシャットダウンされている中で、ひとつの事例として貴重な役割を果たすことになると思います。
本当に、一個のきっかけだけでいいと思っていて。「日本ではこういうふうにやったよ! こっちでもやってるぜ!」みたいな情報が交換できればいいな、というのはすごく感じていますね。いつもは英語と台湾語だけなんですけど、グループ会社のスタッフにフランス人がいたので、お願いしてフランス語でもメッセージを出しました。
手探りな状況の中で、いろいろなところに気を配って対策をしていったわけですね。その繰り返しの中で、コストと対策の落としどころのようなものが徐々に見えていくのではないかと思います。
コストでいうと、スタンディングエリアのフェンスやバリケードは例年の4倍かかっています。桁が一桁上がっています。すさまじい金額がかかったんですけど、安心を買ったんだと思って割り切るしかない。その意識をお客さんが守ってくれたっていうことで、あれはひとつのゴールだったと思います。ただ、それはあくまで今回考えた中でのゴールであって、次の正解を早く見つけたいですね。
“RUSH BALL”は無事に開催できましたが、この経験を踏まえてGREENSさんとしてはこの先の計画をどう考えていますか。
お客さんの意識がまだまだステイホームに近くて、コンサートが開催されてもチケットを買い控えたり、足が重くなったりする人もいる。それは当然ですよね。職場があったり家族がいたり、いろんな状況があるので。
とはいえ、僕らはステージを作らないわけにはいかないので、ひとつでも多くステージを作って、その客席に安全と安心がちゃんとありますよ、と伝えていく。そうやってお客さんに来てもらいたいと日々考えながらも、着々とステージを作っている感じです。
以前の形でライブやコンサートやフェスが開催できる状況が戻ってきたときにも、衛生管理なども含めて、今回の経験がプラスになるのではないかとも思います。
これは僕らの業界だけではなく、新しい普通を作っていかないといけないと思いますね。最初は違和感があるかもしれないけれど、みんなで相談しながらリライトしていって、みんながわかる新しい普通を作っていかなきゃいけない。たとえば、この半年でライブハウスはめっちゃきれいになっていますよ。掃除するしかないので。そういう状態をキープしていきたい。
僕らとしても、やっぱりライブハウスは絶対的になくしたくない。ミュージシャンにとってのいわゆるスタート地点というか、どんなミュージシャンも最初に立つのはライブハウスのステージなので。野外フェスをやったということで、ライブハウスを残す理由と、次の結果につなげる方法、それが次に考えるべきことなんじゃないかなと思っています。

力竹総明さん
PROFILE
大阪のコンサート制作会社、株式会社グリーンズコーポレーションに1997年に入社。1999年に初開催、2005年より大阪府泉大津市で開催されている野外フェス“RUSH BALL”のプロデューサー。
関連記事