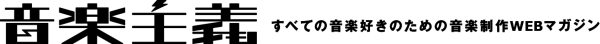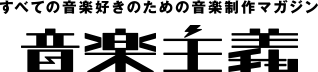vol.46 細野晴臣
-音楽活動50周年-
日本語ロックの礎を築いたはっぴいえんど、テクノミュージックで世界を席捲したYMO、 『銀河鉄道の夜』『万引き家族』のサウンドトラックなど、日本音楽史に数々の功績を 残してきた巨匠が本誌登場!2019年に音楽活動50周年を迎える 細野晴臣さんに、“今”と“未来”についてお聞きした
2019年、細野晴臣が音楽活動50周年を迎える。本人は「それはどうでもいいんです。だって、みんなそうなるでしょ。小坂忠も去年が50周年だったし、幸宏(高橋幸宏)の『サラヴァ!』が40周年。モーニング娘。も20周年だしね(笑)。なので50周年も全然気にしてません。“まだ続けていられるな”という気持ちはあるけどね」とまったく意に介していないのだが、常に変化を繰り返し、そのたびに革新的な音楽を体現してきた細野の半世紀は、日本の音楽シーンにとって、語り尽くせないほどの功績に満ちている。
50周年も全然気にしてません。 “まだ続けていられるな”という 気持ちはあるけどね。
細野晴臣の軌跡
1969年、ロックバンド“エイプリル・フール”のベーシストとしてデビューし、その直後に大瀧詠一、松本隆、鈴木茂と“はっぴいえんど”を結成。バッファロー・スプリングフィールド、CSN&Yなどのアメリカンロックの影響を感じさせるサウンドとともに、日本語ロックの礎を築き上げる。バンド解散後は鈴木茂、林立夫、松任谷正隆らと“日本の ザ・レッキング・クルー”と称すべきキャラメル・ママ(ティン・パン・アレー)を立ち上げ、荒井由実、吉田美奈子、小坂忠、矢野顕子などのレコーディング、プロデュースを担当。そして1978年には高橋幸宏、坂本龍一とともにイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)を立ち上げ、テクノミュージックというまったく新しい概念を掲げた音楽によって、世界を席捲―キャリアのスタートからわずか10数年の時点で、日本のシーンを様変わりさせてきた細野は間違いなく、この国の音楽を語るうえで欠かせない存在だ。
00年代以降もアンビエント、エレクトロニカといった先鋭的な音楽に接近しながら、刺激的な活動を繰り返してきた細野。10年代に入ると、ブギウギ、ラテン、ジャズなどのミッドセンチュリーの音楽に傾倒。高田漣(g)、伊賀航(b)、伊藤大地(dr)、野村卓史(pf)という30〜40代のミュージシャンと生バンドを中心とした活動を行ってきた。2018年もイギリス・ブライトンでの公演“Haruomi Hosono+Acetone Light in the Attic”、カンヌ映画祭でパルムドールを獲得した映画『万引き家族』のオリジナルサウンドトラックの制作など精力的な活動を継続してきたが、次のアクションはなんと1973年のソロデビュー作『HOSONO HOUSE』のリメイクアルバム。先行配信された「薔薇と野獣(new ver.)」のエレクトロファンク的なサウンドからは、現在の細野のモードをはっきりと感じ取ることができる。

「僕たちはこのままで大丈夫なのか?」と、 いろいろと新しいものを聴き始めて、それが 『HOSONO HOUSE』につながったところがある。
『HOSONO HOUSE』1973-2019
1973年にリリースされた『HOSONO HOUSE』は、ソロとしての最初の作品。当時、埼玉県狭山市のアメリカ村に居を構えていた細野は、ティン・パン・アレーのメンバーとともに自宅録音を敢行(レコーディングエンジニアは吉野金次)。ジェイムス・テイラー、ザ・バンドの作品をリファレンスした音像、当時の細野の心象風景を想起させるソングライティングがひとつになった本作は、70年代を代表する名盤としての評価を獲得すると同時に、後進のミュージシャンたちに多大な影響を与えてきた(現在のシーンを代表する星野源もそのひとりだ)。しかし、彼自身は「『HOSONO HOUSE』は自分ではあまり聴かないアルバムだった」という。
「一番最初のアルバムだし、アラが目立つというのかな。当時は自分で音を作っていたわけではないし、狭い部屋で録っていたから、音がまわってしまって、細かいバランス調整もできなくて。それが心残りだったんですよね。名盤? それは自分ではよくわからない(笑)。ただ、『HOSONO HOUSE』をいろんな人が聴いていて、never young beachの安部勇磨くんのように、あのアルバムについて熱く語ってくれる若いバンドマンがいることもわかってきて。あとは“アメリカでも聴かれている”という情報が伝わってきたり、考えを改めましたけどね。そんなこともあって“(リメイクアルバムを)作りませんか?”ということになったのかな。気楽にできると思ってたんだけど、いざやってみたら大変だったんですけどね」
『HOSONO HOUSE』を45年振りにリメイクするにあたって細野は、打ち込みを中心にした制作スタイルを選択。ここ10年ほど生バンドのアンサンブルを追求してきた彼にとっては、久しぶりの音楽的変換と言えるかもしれない。しかし、細野自身も認めているように、新たな打ち込みサウンドを構築するプロセスは、決して簡単なものではなかった。
「あるとき『打ち込みでやるかも』と言ったら、周りの反応が良かったというか、驚く人が多くて。“じゃあ、驚かせてやろう”と思って、1人で作ることにしたんです。一番楽なのはいろんな人にお願いして作ってもらうことなんだけど、今回は腰を据えてやろうかなと。打ち込みの機材もずっとほったらかしだったし、宅録気分でやるのも久し振りだったからね。ただ、そこにいろんな問題があったわけです。この10年くらいは生のバンドが中心だったから、機材が古いままだったんですよ。知り合いのエンジニアと相談して“全部入れ替えなくちゃダメだろう”ということになって、探り探り、機材を新しくし始めて。それもね、最初は1人で右往左往してたんです。渋谷の機材屋に行っても知らない機材ばかりで、何が何だかわからないままボーッと帰ってきたりね(笑)。AKAIのMPCがあったから、“これならわかりそうだな”と思って買ってみたら、パソコンのソフトがないと動かないんですよ。『Standalone』(Akai Professional - The Next Generation of Standalone MPC's)と書いてあるのに、それだけでは音が出ないっていう(笑)。それをやっとつないだところですね、今は。そういうことをやり始めたのが、制作のなかばあたりだったんです。その前に作ったものはやり直したくないので、アルバムにはレコーディングのプロセスが全部出ちゃうでしょうね」
“音”の進化論
打ち込みの機材を全面的に刷新すると同時に、国内外の最新の音楽を久し振りにチェックしてみたという細野。ここ数年は「新しい音楽に興味が持てない。自分にとって未知な音楽は、過去にある」と話していたが(それが20世紀なかばの音楽を追求してきた動機でもあった)、2018年の新しい音楽は、彼にとって大きな発見にあふれていたという。
「遠くから聴いているときはわからなかったんだけど、ヘッドフォンで聴いてみると、ビックリするような世界があったんですよね。それは音楽自体の良し悪しではなくて、音の話なんですけど、この前もラジオで『モーニング娘。に負けた』って言ったら、それが拡散しちゃって。たぶん、最初に変わってきたのはハリウッド映画の音でしょうね。10年くらい前だと思うけど、ハリウッド映画の音響がすごく進化したんですよ。一番顕著なのは重低音。すごく出ているように感じるけど、実際にはそれほど出てないっていう。完璧にシミュレーションされたバーチャルサウンドというのかな。つまり、すべて錯覚なんです。僕は専門家ではないから説明できないけど、おそらくアルゴリズムが完成されていて、すべての音がその範疇にあるんじゃないかな。一番大きな変化は、音楽から音圧が消えたことでしょうね。昔は音圧というものを気にしていたわけですよ。キックが鳴るとスピーカーが揺れたり、ドン!という音が腹に響いたり。それがなくなって、脳内で音圧を感じさせるシステムができあがっているんですよね、今は。それがつまりバーチャルということなんだけど、そういう音の影響は『HOCHONO HOUSE』にもかなり出てくるでしょうね」
テクノロジーの進化によって音響、サウンドメイクの流れが変わり、それが音楽そのもの在り方に多大な影響を与える。この一連の流れは、今に始まったことではない。マルチレコーディングシステムがなければ、ザ・ビートルズの実験的なサウンドは生まれなかったし、MC-8(ローランドのシンセサイザー用シーケンサー)が開発されなかったら、YMOは存在しなかったかもしれない。1973年の『HOSONO HOUSE』もそう。いち早くセルフレコーディングを試していた1970年代前半のアメリカのシンガーソングライター、ロックバンドのサウンドに触発されなければ、『HOSONO HOUSE』のコンセプトは生まれなかったのだから。
「当時はシンガーソングライターたちが作っていた個人的なサウンドに関心があったんですよね。いっぽうでファンク、ソウルミュージックがヒットチャートを賑わせていて、僕は両方とも好きだったんです。どちらの要素も入っているんですよね、あのアルバムには。そう考えると、今の状況と似てますね。『HOSONO HOUSE』を作る前は、鈴木茂と古い音楽ばかり聴いてたんですよ。ガーシュウィンとかね。ディスクユニオンのヴィンテージコーナーに通って、1930年代のレコードを買って。それを1年くらい続けた頃に茂が『僕たちはここのままで大丈夫なのか?』と言い出したんだけど、ちょうどその頃、スライ&ザ・ファミリー・ストーンの『Fresh』を聴いて、“これはすごい”と思って、いろいろと新しいものを聴き始めて、それが『HOSONO HOUSE』につながったところがあるので」

今のサウンドを利用しながら、個人の音楽として出して いる人もいる。アンチグローバリズムの音楽というか。 自分は後者なんですよね、どちらかと言えば。
音楽の在り方
さらに細野は「こういうサウンドの変化は10年に1回くらいあって、いつもそういう変化にさらされてきた世代なんですよ、我々は」と言葉をつなげる。
「50年代と60年代の音も全然違うし、今聴いても“これは80年代の音だな”とわかりますからね。90年代以降もそうですよ。まずアンビエントがあって、それが00年代のエレクトロニカにつながって。それは音楽が環境を取り込んでいった時期ですよね。音楽の上に環境音やノイズを乗せるのではなく、それ自体を取り込みながら表現している人たちが出てきて―それも個人の音楽ですよね―僕も“どうやって作っているんだろう?”と興奮して、手作りでやってみたりね。それがSKETCH SHOWの1枚目(『AUDIO SPONGE』/2002年)なんです。その後、“このソフトを使えば、いとも簡単にできる”ということがわかって、途端につまらなくなっちゃった(笑)。今のバーチャルなサウンドも、いずれはそうなるでしょうけどね。エレクトロニカが衰退したのも、ソフトがアップデートされて、当時の機材が使えなくなったことが一因ですから。ずっとそういうことを繰り返しているんですよ」
ここで強調しておきたいのは、新たにリリースされる『HOCHONO HOUSE』は、単にサウンドをアップデートさせただけの作品にはなり得ないということだ。このアルバムの魅力の中心であるソングライティング技術の高さ、普遍性としか言いようがない歌の素晴らしさを残しながら、現在進行形のサウンドメイクと同期させることこそが、本作の骨子。もっとも重要なのは、ソロアーティストとしての原点である『HOSONO HOUSE』に込められた作家性なのだと思う。
「エド・シーランという人がいますよね。彼の音楽の作り方は非常に面白いと思うんですよ。1人でライブができるとかね。でも、レコーディングされた音源を聴くと、世界標準に組み込まれてしまっている。本当はもっととがっていて、デコボコしているはずなのに、すべて平均化されるというか。そうではなくて、今のサウンドを利用しながら、個人の音楽として出している人も出てきているんだよね。アンチグローバリズムの音楽というか。自分は後者なんですよね、どちらかと言えば」
『HOCHONO HOUSE』のほか、2019年1月には特別番組『細野晴臣イエローマジックショー2』が放送されるなど、50周年に向けて幅広い活動が予定されている。自ら作り上げてきたスタイルにとどまることなく、常に新しい刺激を求めながら、リスナーの想像を超えた音楽を発信してきた細野晴臣。「20数年振りの大変革かもしれない」という現在のモードがどんな楽曲に結びつくか、おおいに期待したいと思う。
PROFILE
1947年、東京生まれ。1969年にエイプリル・フールでデビュー。1970年には、はっぴいえんどを結成。解散後の1973年にソロ活動を開始、同時にティン・パン・アレーを立ち上げ、多数のアーティストへの楽曲提供やプロデュースを行う。1978年にはYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)を結成。YMO散開後は、レーベル主宰、ワールドミュージックやアンビエントミュージックの探求、作曲、プロデュース、俳優など、多岐にわたって活動している。音楽活動50周年となる2019年3月にニューアルバム『HOCHONO HOUSE』をリリース。現在はツアー中で、2月23日(土)台北でツアーファイナルを迎える。
RELEASE INFORMATION

new album『HOCHONO HOUSE』
ビクター/VICL-65086、VIJL-60196?60197(アナログ盤)/2019年3月6日発売。
関連記事